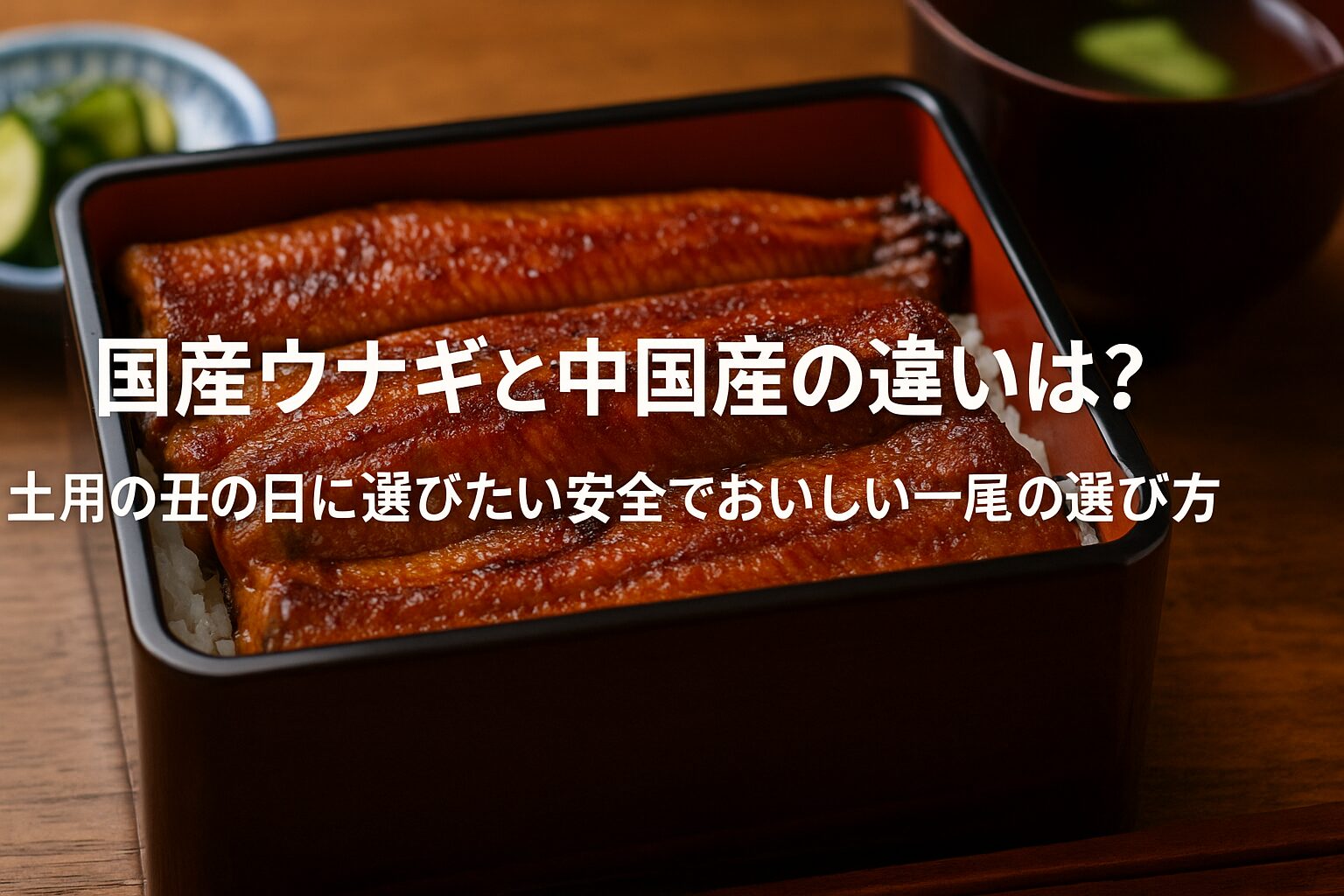毎年やってくる「土用の丑の日」。スーパーや飲食店にウナギがずらりと並び、「今年はどれを選ぼうかな」と迷ったことはありませんか?
ウナギは夏バテ対策にぴったりのスタミナ食ですが、国産と中国産では何が違うのか、なんとなく不安…という方も多いはず。
この記事では、ウナギの栄養・産地ごとの違い・安全性・おすすめの選び方まで、わかりやすく丁寧に解説します。
2025年の土用の丑の日(7月19日)には、自信を持って「おいしくて安心な一尾」を選べるようになります
土用の丑の日にウナギを食べる理由

「土用の丑の日」とは、1年のうちでも特に暑さが厳しくなる夏の時期にあたり、古くから「体調を崩しやすい日」として知られてきました。季節の変わり目にあたる「土用」に、十二支の「丑(うし)の日」が重なるこの日は、疲れやだるさが出やすくなるタイミング。そんなとき、体にパワーを与えてくれる食べ物として重宝されてきたのがウナギです。
この習慣は、実は江戸時代の頃から続いている伝統のひとつ。当時の学者・平賀源内が「う」のつく食べ物を夏に食べるといいと広めたことがきっかけとされています。その中でも栄養が豊富で、体力回復にぴったりなウナギが注目され、やがて夏バテ予防の“スタミナ食”として定着しました。
2025年の土用の丑の日は7月19日(土)。この日が近づくと、スーパーや飲食店の店頭にはずらりとウナギのかば焼きや白焼きが並び、まさに“食べなきゃ損”という雰囲気に包まれます。暑くて食欲が落ちがちな時期でも、あの香ばしい香りや甘辛いタレの香りをかぐと、「やっぱり今年も食べたい」と思う方も多いのではないでしょうか。
しかも、ウナギにはタンパク質やビタミン、DHA・EPAなどの栄養素がたっぷり。単なる夏の風物詩ではなく、理にかなった「栄養補給食」でもあるんです。
つまり、「土用の丑の日にウナギを食べる」ことは、ただの風習ではなく、夏を元気に乗り切るための、実に理にかなった食文化。今年は、体へのごほうびとして、ぜひウナギを味わってみてはいかがでしょうか?
ウナギの栄養価は?スタミナの秘密
ウナギは見た目以上に栄養たっぷりの食材です。まず注目したいのがタンパク質。100gあたりに23gも含まれており、1尾まるごと食べれば約34.5gのたんぱく質を摂取できます。これだけでかなりのエネルギー補給になります。
さらに、ビタミンAも豊富。これは目の健康や肌のうるおい、粘膜の強化に欠かせない栄養素です。1尾食べれば1日分をほぼカバーできる量ですが、毎日大量に摂ると過剰になりやすいので、食べすぎには少し注意が必要です。
また、疲労回復に役立つビタミンB群(B1・B2・B6)も豊富です。特にB1は、糖質をエネルギーに変えるサポートをしてくれるので、夏バテ防止にぴったり。
そして、最近注目されているDHA・EPAもたっぷり含まれています。これらは青魚に多いことで知られていますが、実はウナギにも同じくらい含まれていて、脳の働きをサポートしたり、血液をサラサラにする効果も期待できます。
国産と中国産、どう違うの?

スーパーに並ぶウナギのパッケージには、「国産」や「中国産」と書かれていることがあります。でも、見た目ではその違いがわかりにくく、「結局どちらがいいの?」と迷う人も多いのではないでしょうか。
実は国産ウナギは、日本国内で育てられたもので、水質やエサ、育成環境などに細かくこだわって養殖されています。一般的に味が濃くて身がふっくらしており、香ばしさも際立ちます。そのぶん価格は高めですが、安全性や品質に安心感があります。
一方、中国産ウナギは輸入品で、以前は薬剤の使用や水質問題が取り上げられたこともありますが、近年は基準が厳しくなり、改善が進んでいます。コストパフォーマンスは非常に高く、リーズナブルにウナギを楽しみたい方にとっては選択肢のひとつです。
味の違いは、使われているタレや焼き方にも左右されるため、一概には言えませんが、濃厚な味わいを求めるなら国産、コスパ重視なら中国産と覚えておくと選びやすくなります。
中国産ウナギって本当に安全なの?
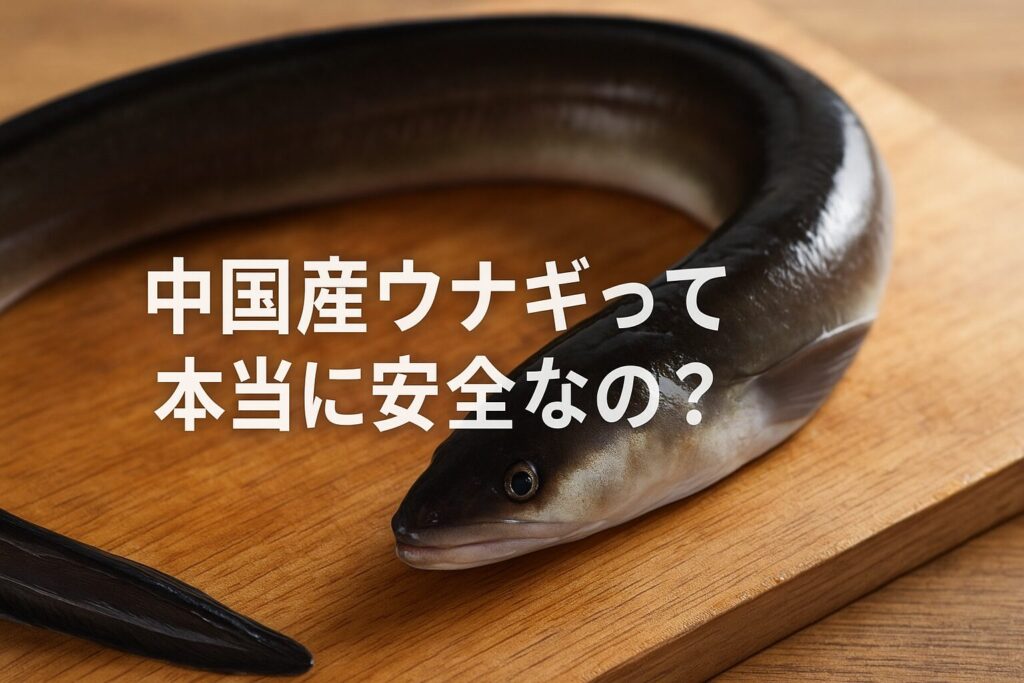
「中国産ウナギ=危ない」というイメージを持っている方も少なくありません。実際、2000年代には抗生物質や残留薬剤の問題が報道されたこともあり、不安が残っている方も多いのが現状です。
ですが、現在日本に流通している中国産ウナギの多くは、厳しい食品検査をクリアしており、安全性は年々向上しています。
✅ 安全性が向上している理由
日本への輸入時に、残留農薬や抗生物質の検査が義務付けられている
加工段階でも、日本企業や合弁会社が管理する施設が増えている
養殖方法の改善により、水質・エサ・育成環境が国際基準に近づいている
つまり、信頼できるルートで輸入・加工されている中国産ウナギであれば、安全性は十分に確保されていると言えます。
✅ 安心して中国産ウナギを選ぶ3つのポイント
パッケージに「加工地・養殖地・輸入者」が明記されているものを選ぶ
→ 表示義務があるので、信頼できるかを確認する手がかりになります。
スーパーや百貨店、業務用の実績がある店舗で購入する
→ 取引の多い店舗はリスク管理に厳しく、粗悪品が出回りにくいです。
国産ウナギと比較して「安すぎる」商品は注意する
→ 極端に安価な商品は、加工・流通の情報が曖昧なことも。価格だけで選ばず、情報がしっかり開示されている商品を選びましょう。
「なんとなく不安」で中国産ウナギを避けてしまうのはもったいないかもしれません。正しく選べば、おいしくて安心して食べられる商品もたくさんあります。
また、予算や家族構成、食べる頻度に応じて、国産と中国産を使い分けるのも賢い選択です。
大切なのは「どこで作られたか」よりも、「どう管理されているか」。
信頼できる情報をもとに、納得のいく選び方をしていきましょう。
🇯🇵 厚生労働省のモニタリングで分かった中国産ウナギの安全性
✅ マラカイトグリーン(着色剤)の検出
厚労省は、輸入時の検査で中国産養殖ウナギからごく微量のマラカイトグリーン(0.044ppm、0.006ppm)が検出されたと報告しています。ただし、このレベルでは通常の摂取量では健康への影響はないとされています(2022年実施)。
✅ 抗菌剤エンロフロキサシンの監視
2024年11月、厚労省が発表した輸入ウナギのモニタリングで、中国産養殖活ウナギおよびその加工品に含まれるエンロフロキサシン(抗菌剤)が一部で基準値を超えたとして、製造・輸出者名が公表されました。ただし、これもごく一部の事例で、今後は検査強化が行われています。
✅ 継続的な輸入食品監視の実施
厚労省は、年ごとの「輸入食品監視指導計画」で、輸入ウナギやその他魚介類を対象に抗生物質・残留農薬・添加物などのモニタリング検査を継続しています。不検出が大半ですが、違反検出があれば輸入差止めや回収命令などの対応をとる体制が整っています。
安心して中国産ウナギを選ぶために
微量検出でも、通常の食べ方では安全性に問題なし
マラカイトグリーン検出はあるものの、健康影響なしとされています。
違反があれば即対応されるシステムがある
エンロフロキサシンなどの基準超過があれば、輸入停止・公表される対策が取られます。
信頼できる販売業者や流通経路を選ぶことが重要
表示がしっかりしていて、検査体制が明示されている商品が安心です。
微量でも検出されたケースはあるが、「通常の食事量では心配ないレベル」と厚労省が明言している。
抗菌剤の一部基準超過例もあるが、政府は輸入検査を強化し、問題があれば迅速に対応。
消費者としては、産地や検査情報が明示されている信頼できる商品を選ぶのが安心。
国産・中国産の使い分けもOK。安全性への不安は減ってきており、どちらも賢く選んで楽しめます。
消費者庁の輸入ウナギ検査報告
中国産ウナギにおける薬剤検出の経緯と対応
消費者庁は食品中の残留農薬などをモニタリングする調査を毎年実施しています 。
過去には、中国産冷凍ウナギにマラカイトグリーンが検出された報告もありました 。
これは、ウナギ養殖に使用された着色や抗菌作用のある薬剤で、当時大きな話題となりました。
その後、2005年に規制強化されたことで使用は減少し、現在ではほとんど検出されなくなっています。消費者庁が公表する「食品中の残留農薬等一日摂取量調査(令和5年度)」でも、輸入ウナギの検査において基準値を超えた報告はほぼないことが読み取れます 。
✅ 安全性向上の背景と現状
薬剤使用の規制強化でマラカイトグリーンの使用が大幅に減少。
消費者庁による年次の残留農薬調査でも問題なしと判断。
「基準値超過」や「健康リスク」が取りざたされることは、今ではごく少数の事例に限られています。
かば焼きと白焼き、どちらがヘルシー?
ウナギの食べ方といえば、多くの人が思い浮かべるのがかば焼き。甘辛いタレが食欲をそそり、ごはんとの相性もバツグンです。ただ、タレには砂糖やしょうゆがたっぷり使われているため、カロリーは高めになります。
一方の白焼きは、タレを使わずに素焼きで仕上げたもの。塩やわさび醤油でシンプルに楽しむのが一般的で、素材の味がしっかり感じられるのが特徴です。カロリーはかば焼きより低く、脂質や塩分を控えたい方におすすめです。
また、白焼きはDHAやEPAなどの良質な脂をしっかり摂れるうえに、胃にもやさしいため、高齢者にも向いています。
「こってり派」はかば焼きを、「あっさり派」は白焼きを選ぶなど、その日の体調や気分に合わせて使い分けると、より健康的に楽しめます。
| 焼き方 | 特徴 | カロリー | 塩分 |
| かば焼き | 甘辛ダレがご飯に合う | 高め(約300kcal/100g) | 多め |
| 白焼き | 素焼きで素材の味 | 低め(約200kcal/100g) | 少なめ |
栄養バランスを整える副菜のヒント

ウナギは栄養たっぷりですが、脂質も多いため、一緒に食べる副菜でバランスを整えることが大切です。栄養バランスを考えたときにおすすめなのが、酸味やビタミンCが豊富な副菜です。
たとえば:もずく酢・わかめ酢:さっぱりして消化もよく、食欲が落ちているときでも食べやすい。
ブロッコリー・パプリカサラダ:ビタミンCが豊富で、鉄分やたんぱく質の吸収をサポート。
豆腐入り味噌汁:良質な植物性タンパク質を補いながら、胃腸にもやさしい。
ウナギのように主役の料理が濃厚なときこそ、副菜で口の中をリセットするような役割があると、最後まで飽きずに食べられて、体にも優しい献立になります。
最後に・土用の丑の日は、ウナギを知っておいしく食べるチャンス

土用の丑の日は、夏の疲れを吹き飛ばすスタミナ食・ウナギを楽しむ大切な日です。ウナギには、タンパク質やビタミンA・B群、DHA・EPAなど、元気な体づくりに役立つ栄養がたっぷり詰まっています。
そして、国産ウナギと中国産ウナギの違いを知っておくことは、安全でおいしい一品を選ぶうえでとても大切です。産地による味や価格、安全性の違いを正しく理解することで、より納得して選べるようになります。
また、かば焼きと白焼きの特徴やカロリーの違い、副菜で栄養バランスを整えるコツを押さえておけば、ウナギをもっとおいしく、そして健康的に楽しむことができます。
今年の土用の丑の日(2025年7月19日)は、ただ「ウナギを食べる」だけでなく、栄養と産地の違いを知って、自分に合った一皿を選ぶチャンスとして、ぜひ役立ててください。
“おいしくて体にもうれしい”ウナギで、夏の元気をチャージしましょう!