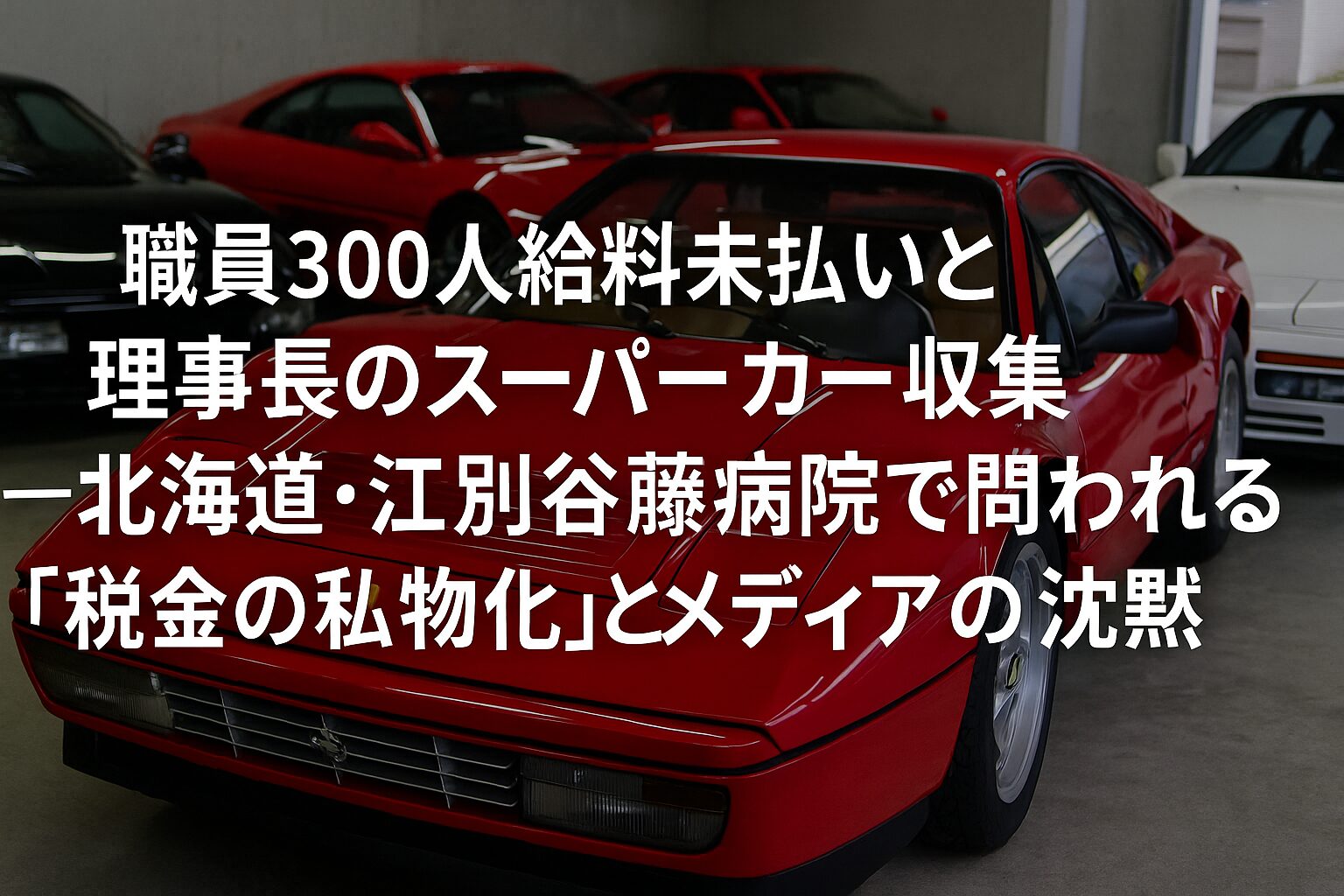北海道札幌市のベッドタウンとして発展してきた江別市。人口約12万人が暮らすこの街で、地域医療の重要な砦とされてきた「江別谷藤病院」が、今、深刻な事態に揺れている。約300人に及ぶ職員が2ヶ月以上もの間、給与を受け取れないという異常事態。二次救急や夜間診療を担い、市民の命を守る最前線であるはずの場所で、そこで働く人々の生活が根底から脅かされているのだ。
しかし、この問題は単なる「経営難」の一言で片付けられるものではない。職員たちが生活費の工面に喘ぐ一方で、病院のトップである谷藤方俊理事長が、1台数千万円は下らないスーパーカーを複数台コレクションし、その華やかな趣味をSNSで誇示していたという驚くべき実態が明らかになったからだ。
本稿は、江別谷藤病院で起きた給与未払い問題を丹念に追い、その根底に横たわる日本の医療法人が抱えるガバナンスの欠如、税制優遇制度の歪み、そして問題の本質から目を背ける地元メディアの構造的怠慢を白日の下に晒すものである。これは江別市だけの問題ではない。我々が納める税金や社会保険料が、意図せぬ形で個人の欲望を満たすために使われているかもしれないという、日本全体の医療システムに対する警鐘なのだ。
第一章:生活の糧を絶たれた医療従事者たちの悲鳴
突如訪れた「無給」という現実
事態が表面化したのは2025年の夏。江別谷藤病院に勤務する看護師、介護士、理学療法士、事務職員など約300人の職員に対し、本来支払われるべき給与の支給が突如として停止された。最初の遅延から2ヶ月が経過しても、事態は改善の兆しを見せず、職員たちの生活は困窮を極めている。
被害に遭っている職員の多くは、地域の医療を支えるという使命感と共に、日々の生活をその給与に依存している人々だ。パートや契約職員として家計を支える女性、住宅ローンや子どもの教育費を抱える世帯主も少なくない。「来月の家賃が払えない」「子どもの給食費をどうすればいいのか」。悲痛な声が院内に渦巻くが、病院側からの明確な説明や救済策は示されていない。
ある職員は匿名を条件にこう語る。「説明会は開かれましたが、理事長からは『地域医療を止めるわけにはいかない。皆で頑張ろう』という精神論ばかり。私たちが聞きたいのは、いつになったら給料が支払われるのか、という一点だけです。しかし、その具体的な日付は一度も明言されませんでした。まるで、私たちの生活など存在しないかのような扱いです」。
この対応は、労働者の権利を保護する労働基準法第24条(賃金全額払いの原則)に明確に違反する可能性がある。しかし、職員たちは「ここで声を上げれば解雇されるかもしれない」「病院が潰れてしまえば、地域の患者さんが路頭に迷う」という恐怖と責任感の板挟みになり、強く抗議できない状況に追い込まれている。まさに、医療従事者の良心と生活を人質に取った、悪質な経営判断と言わざるを得ない。
「地域医療のため」という言葉の欺瞞
病院側が繰り返す「地域医療を止めるわけにはいかない」という言葉は、一見すると崇高な理念に聞こえる。しかし、その実態は、経営責任の放棄と職員への責任転嫁に他ならない。地域医療を維持するための最低条件は、そこで働く職員の生活基盤を保障することである。その根幹を揺るがしておきながら「地域医療のため」と語る資格が、果たして現経営陣にあるのだろうか。
給与の遅配・未払いは、職員の士気を著しく低下させ、医療の質の低下に直結する。集中力を欠いた状態で医療行為を行うことは、重大な医療過誤を引き起こすリスクを増大させる。つまり、給与未払いを放置すること自体が、「地域医療を危険に晒す」行為なのである。この矛盾に経営陣が気づいていないとすれば、あまりにも経営者としての資質を欠いていると言えるだろう。
第二章:理事長の「大人のオモチャ箱」と職員の絶望
職員たちが絶望の淵に立たされている一方で、谷藤方俊理事長のプライベートは、煌びやかな光に満ちていた。その実態が露見したのは、彼が使用していたとみられるインスタグラムの「裏アカウント」の存在だった。
SNSで誇示された2億円超のコレクション
「masatoshii131」というアカウント名で(現在は削除済み)、谷藤理事長は自らのスーパーカーコレクションを惜しげもなく公開していた。そこには「大人のオモチャ箱」と称された巨大なガレージに、赤や黒のフェラーリが9台も整然と並ぶ圧巻の写真が投稿されていた。
確認できる車種だけでも、市場価格で5000万円を超えることもある1970年代の伝説的な名車「フェラーリ 512BBi」をはじめ、現代のモデルに至るまで、フェラーリだけで数億円規模のコレクションとみられる。さらに、複数のポルシェや国産の高級スポーツカーも所有していることが投稿から判明しており、車両資産の総額は、控えめに見積もっても2億円を優に超えると推測される。
衝撃的なのは、その投稿のタイミングだ。給与未払いが深刻化するわずか2週間前、谷藤理事長は前述の「フェラーリ 512BBi」で小樽運河沿いを優雅にドライブする動画を投稿していた。職員たちが、月末の支払いを前に不安な夜を過ごしていたであろうその時、経営の最高責任者は、エンジン音を高らかに響かせ、趣味の世界に没頭していたのだ。この事実が、職員たちに与えた精神的ダメージは計り知れない。それは単なる給与の遅延ではなく、自らの尊厳を踏みにじられたと感じさせるに十分な、裏切り行為であった。
1台の売却で救える命と生活
仮に、コレクションのうち1台、例えば市場価格3000万円のフェラーリを売却したとしよう。職員300人の平均月収を仮に30万円と仮定すれば、月々の総支給額は9000万円となる。3000万円あれば、全職員の給与の3分の1を即座に支払うことができる。希少価値の高いモデルであれば、1台で1ヶ月分の給与を全額賄うことさえ可能かもしれない。
つまり、この問題は「資金がない」という単純な経営難ではない。経営者が、職員の生活を守るための資金を捻出する意思があるかどうかという、「経営姿勢」と「価値観」の問題なのである。自らのコレクションに手を付けず、職員の犠牲の上に「地域医療」を語る姿は、多くの人々の目に偽善としか映らないだろう。
第三章:税制優遇は誰のためか? 医療法人のブラックボックス
なぜ、一病院の理事長がこれほどまでの富を築き、それを個人の趣味に投じることができたのか。その背景には、日本の医療法人が享受する手厚い税制優遇措置と、その運用の不透明さという構造的な問題が存在する。
「非営利」を盾にした巨大な優遇
江別谷藤病院のような地域医療を担う医療法人の多くは、その公共性・非営利性を理由に、一般企業とは比較にならないほどの税制上の優遇を受けている。
消費税の非課税: 診療報酬など、社会保険医療に係る収入には消費税が課されない。
法人税の軽減: 特定の要件を満たす医療法人(社会医療法人など)は、法人税率が大幅に軽減される。
固定資産税・都市計画税の減免: 病院の建物や土地にかかる税金が減免される場合がある。
補助金の交付: 高額な医療機器の導入などに対し、国や地方自治体から多額の補助金が交付される。
これらの制度はすべて、「利益追求を目的とせず、地域医療に貢献する」という崇高な理念を支えるために設計されている。つまり、その原資は国民が納めた税金や社会保険料に他ならない。しかし、この制度がひとたび悪用されれば、国民の善意が一部の経営者の私腹を肥やすための「錬金術」と化してしまう危険性を孕んでいる。
理事長の「おもちゃ」は誰の資産か
問題は、法人と個人の資産の境界線が極めて曖昧になりがちな点だ。例えば、谷藤理事長のスーパーカーが「医療法人の資産」として購入・維持されていた可能性もゼロではない。「理事長の移動用」「広報・宣伝用」など、名目さえ立てれば、法人の経費として高級車を所有することは不可能ではない。その場合、車両の購入費用、保険料、維持費のすべてが法人の経費となり、結果的に法人税の支払額を圧縮することに繋がる。
もし、これらの車が法人名義であったとすれば、それはまさに税制優遇制度の私物化であり、国民に対する背信行為だ。仮に個人名義であったとしても、その購入資金の源泉が、医療法人から支払われる高額な役員報酬であるとすれば、問題の本質は変わらない。医療法人の収益は、本来、医療の質の向上、職員の待遇改善、そして将来の設備投資に再分配されるべきものであり、理事長個人の贅沢な趣味のために費やされるべきではないからだ。
この構造をチェックすべき監督官庁(都道府県)の監査も、多くは書類上の形式的な確認に留まり、経営者の資産形成や経費の使途といった実質的な部分にまで踏み込むことは稀だ。結果として、医療法人の経営は外部から見えにくい「ブラックボックス」となり、一部の経営者による独裁的な運営と資産の私物化を許す温床となっている。
第四章:沈黙する地元メディアと「美談」の罠
この深刻な人権侵害と制度の歪みに対し、地域の監視役であるべき地元メディアは、その役割を果たしていると言えるだろうか。残念ながら、答えは「否」である。
HTB北海道テレビなど一部の地元メディアの報道は、「給与未払いの中でも、使命感を持って働き続ける職員たち」「地域の灯を消すな!病院を支えよう」といった論調に終始している。これは一見、職員や地域に寄り添った報道に見えるが、その実態は、問題の核心を巧みに隠蔽する「美談化」に他ならない。
なぜ理事長の責任を追及しないのか
これらの報道では、なぜ給与未払いが起きたのか、その経営責任は誰にあるのか、そして理事長の豪奢な私生活と今回の事態との関連性といった、最も重要な点がほとんど報じられない。本来であれば、ジャーナリズムは権力や資本を監視し、不正を告発する使命を負うはずだ。しかし、江別谷藤病院の件では、その牙は完全に抜かれている。
背景には、メディアと地域の有力な機関(大病院など)との間に存在する、構造的な「もたれ合い」の関係が指摘できる。大病院は、地域における大口の広告スポンサーであり、メディアにとって「お客様」でもある。また、日々のニュースソースとしても重要な存在だ。こうした関係性が、メディアの追及を鈍らせ、経営者に不都合な真実から目を背けさせる忖度を生む。
この「茶番報道」がもたらす害悪は計り知れない。第一に、被害者である職員を「美談の主人公」に仕立て上げることで、彼らが抱える生活の困窮や経営陣への怒りといった生々しい現実を覆い隠してしまう。第二に、問題の本質を「経営難」という不可抗力的なものに矮小化し、谷藤理事長個人の経営責任を曖昧にしてしまう。結果として、根本的な解決は先送りされ、職員はさらなる我慢を強いられることになるのだ。
第五章:背任か、経営判断か?浮かび上がる新たな疑惑
問題の根は、さらに深いところにある可能性が浮上している。それは、谷藤理事長と、北海道の医療業界でその名を知られる特定の医師との関係だ。
“DJドクター”との接点
道内には、医師不足に悩む地方病院に高額な報酬で医師を派遣するビジネスで知られ、派手な私生活から“DJドクター”とも揶揄される整形外科医が存在する。この人物と谷藤理事長は、スーパーカー収集という共通の趣味を通じて親交があったとの情報がある。
ここで重大な疑惑が持ち上がる。病院が全職員への給与支払いを停止するほどの資金難に陥りながら、特定の派遣医師に対しては、通常よりも高額な報酬を支払い続けていたのではないか、という可能性だ。特に、理事長と個人的な繋がりを持つ医師が優遇されていたとすれば、それは単なる経営判断のミスでは済まされない。
これは、会社(医療法人)の財産を不当に流出させ、法人に損害を与える「背任行為」(刑法第247条)に該当する可能性がある。背任罪は、自己または第三者の利益を図る目的で任務に背く行為を罰するものであり、証明されれば刑事罰の対象となる。
もし、職員300人の生活を犠牲にしてまで、個人的な繋がりのある特定の人物に利益を供与していたのであれば、それはもはや経営者失格どころか、法的に断罪されるべき行為である。この不透明な資金の流れについて、徹底的な調査と真相究明が求められる。
結論:我々は何を守るべきなのか?
江別谷藤病院の問題を前に、我々は改めて問わなければならない。「病院を守る」とは、一体何を意味するのか。それは、単に病院という建物を存続させることではない。そこで働く職員一人ひとりの生活と尊厳を守り、公正で透明な経営のもとで、質の高い医療サービスが地域に提供される体制を守ることだ。
そのために、今、必要なのは感情的な美談ではなく、痛みを伴う構造改革である。
医療法人のガバナンス強化: 理事長の権限が過度に集中しないよう、監事や評議員会の機能を強化し、外部からのチェックが実効性を持つ仕組みを構築すべきである。経営状況に関する情報公開を徹底し、経営の透明性を確保することも不可欠だ。
税制優遇制度の厳格な運用: 医療法人への税制優遇は、あくまで「地域医療への貢献」という目的に沿って運用されなければならない。監督官庁は、経費の使途や役員報酬の妥当性について、より踏み込んだ監査を行うべきであり、制度の趣旨から逸脱した法人に対しては、優遇措置の停止や取り消しも含めた厳しい姿勢で臨む必要がある。
メディアと市民の監視機能: メディアはスポンサーへの忖度を乗り越え、権力の監視という本来の役割を果たすべきだ。そして、我々市民もまた、「お任せ」の姿勢を改め、自らが支払う税金や保険料がどのように使われているのかに関心を持ち、不正に対しては厳しく声を上げる「賢明な主権者」でなければならない。
谷藤理事長は、所有するスーパーカーを売却すれば、未払い賃金を即座に支払うことができるはずだ。それを行わないという選択は、この問題が「経営危機」ではなく、経営者の倫理観と価値観の欠如に起因する「人災」であることを雄弁に物語っている。
江別谷藤病院の悲劇を繰り返さないために、我々はこの事件を一個人の資質の問題として終わらせてはならない。これは、日本の医療制度が抱える根深い病巣の表出であり、社会全体で取り組むべき改革の出発点なのである。公正で透明な経営を求め、私利私欲による公的制度の私物化を許さない―その断固たる姿勢こそが、真の意味で地域医療を守る唯一の道なのだ。