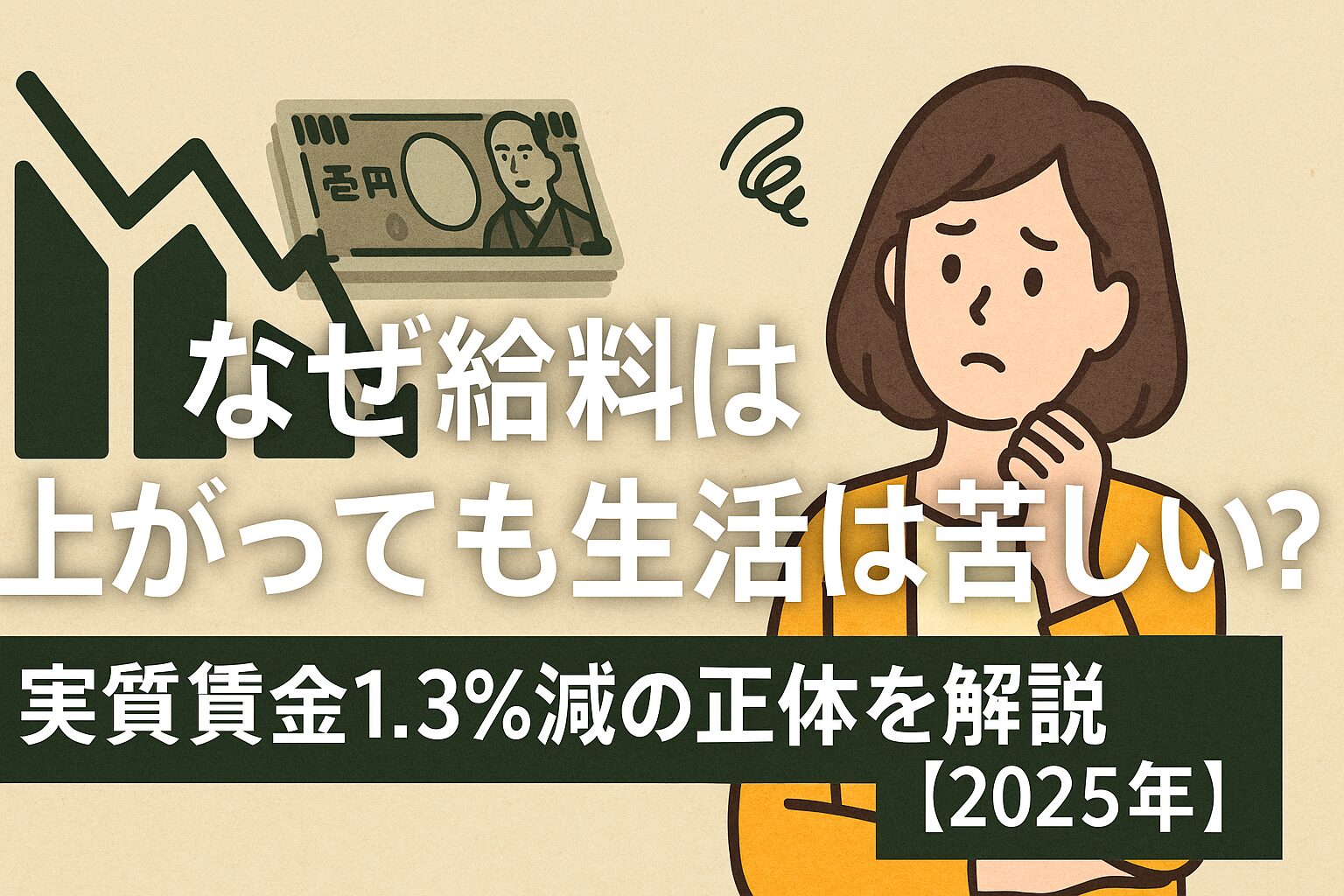「給料は少し上がったはずなのに、なぜか生活は楽にならない…」。多くの人が、そんな実感を持っているのではないでしょうか。2025年6月、日本の実質賃金は前年に比べて1.3%減少し、6カ月連続のマイナスとなりました。一方で、物価の上昇率は3.8%を記録し、私たちの家計を圧迫し続けています。
この記事では、なぜ「名目賃金」が上がっても「実質賃金」が下がり、私たちの実質購買力が低下しているのか、その構造的な理由を分かりやすく解き明かします。さらに、政府や日本銀行の政策が私たちの生活にどう影響するのか、そしてこの厳しい状況を乗り切るための具体的な対策まで、専門的な視点から徹底解説します。
2025年6月の実質賃金の動向

手取り額が増えても、買えるものが減っている。これが今の日本の現状です。ここでは、発表されたデータが私たちの財布にどう直結しているのかを解説します。
前年同月比1.3%減、6カ月連続マイナスの意味
2025年6月の実質賃金が1.3%減少したという事実は、私たちの「お金の価値」が実質的に目減りしたことを意味します。実質賃金とは、受け取る給与の額面(名目賃金)から物価の上昇分を差し引いて計算される指標で、いわば「給料で実際にどれだけのモノやサービスが買えるか」を示す購買力そのものです。
これが6カ月連続でマイナスということは、半年もの間、賃金の伸びが物価の上昇ペースに全く追いついていない状況が続いていることを示します。たとえ給与明細の数字が増えていたとしても、それ以上に物価が上がっているため、結果として昨年よりも買えるものが少なくなっているのです。この状況は、生活者の節約志向を強め、消費の停滞を招くことで、日本経済全体に悪影響を及ぼす懸念があります。
名目賃金2.5%増加とのギャップと要因
多くの人が混乱するのが、「名目賃金は2.5%増えている」という事実です。名目賃金とは、私たちが給与明細で目にする額面の金額そのものを指します。確かに、多くの企業が賃上げを実施し、給料の額は増えました。
しかし、なぜ生活が楽にならないのでしょうか。その答えは、3.8%という高い物価上昇率にあります。計算式で示すと非常にシンプルです。
名目賃金の伸び率 (2.5%) – 物価上昇率 (3.8%) = 実質賃金の伸び率 (-1.3%)
つまり、給料が2.5%上がっても、モノの値段が3.8%も上がってしまえば、実質的な購買力は1.3%分だけ下がってしまうのです。この名目賃金と実質賃金のギャップこそが、「給料は上がったはずなのに生活が苦しい」と感じる正体です。この背景には、後述する歴史的な円安や原材料価格の高騰といった、個人の努力だけではどうにもならない経済構造の問題が存在します。
物価上昇と生活への影響

スーパーでため息をつく回数が増えたかもしれません。特に食料品の値上がりは深刻で、私たちの生活に直接的な打撃を与えています。
消費者物価3.8%上昇(特に食品)の背景
今回の物価上昇率3.8%という数字は、日本銀行が目標とする2%を大きく上回る水準です。この高インフレの主な背景には、複数の要因が複雑に絡み合っています。
第一に、歴史的な円安の進行です。円の価値が下がると、海外から輸入する原材料やエネルギーの価格が国内で割高になります。日本は食料やエネルギーの多くを輸入に頼っているため、円安はガソリン代や電気代、そしてパンや麺類といった加工食品の価格を直接押し上げます。
第二に、世界的な原材料価格の高騰です。不安定な国際情勢や世界的な需要の増加により、原油や穀物などの国際商品価格が高止まりしています。
そして第三に、国内の深刻な人手不足です。物流業界やサービス業などで人件費が上昇しており、そのコストが商品やサービスの価格に転嫁され始めています。特に生活に身近な食品価格の上昇が顕著なのは、こうした輸入コストと国内の人件費上昇のダブルパンチを受けているためです。
賃金が追いつかないことで起こる購買力低下
「物価上昇に賃金が追いつかない」状況が続くと、私たちの実質購買力は確実に低下します。例えば、昨年1万円で買えていた食料品や日用品の詰め合わせが、今年は1万380円出さないと買えなくなったとします。しかし、給料が1万円から1万250円にしか増えていなければ、同じものを買うことすらできません。
このような購買力の低下は、まず家計の支出見直しにつながります。外食を控えたり、旅行を中止したり、より安いプライベートブランド商品を選んだりと、消費行動はどんどん防衛的になります。これが社会全体で広がると、企業の売上が減少し、設備投資やさらなる賃上げへの意欲が削がれるという悪循環に陥りかねません。個人の生活レベルの低下だけでなく、経済全体の活力を失わせる深刻な問題なのです。
政府・金融政策当局の対応と懸念

この厳しい状況に対し、政府と日本銀行も手をこまねいているわけではありません。しかし、その政策には期待と同時に課題も存在します。
最低賃金6%引き上げ提案の狙いと課題
政府は、経済の好循環を実現するための一つの策として、最低賃金を6%引き上げるという意欲的な提案をしています。この狙いは、賃金の底上げを通じて、低所得者層の生活を支え、国全体の消費を喚起することにあります。最低賃金が上がれば、パートやアルバイトなど非正規雇用者の収入が増え、それが正規雇用者の賃金引き上げにも波及効果をもたらすことが期待されます。
しかし、この政策には大きな課題も伴います。特に、経営体力に乏しい中小企業にとっては、急激な人件費の上昇は死活問題になりかねません。コスト増加分を商品やサービス価格に転嫁できなければ収益が悪化し、最悪の場合、雇用の抑制や倒産につながるリスクがあります。また、価格転嫁が進めば、それがさらなる物価上昇を招き、結局実質賃金が上がらないという「いたちごっこ」に陥る可能性も指摘されています。最低賃金引き上げの影響は、プラスとマイナスの両側面を慎重に見極める必要があります。
金融政策(利上げ・物価目標)の視点からの対応
一方、物価の安定を使命とする日本銀行は、難しい舵取りを迫られています。3.8%という物価上昇は、日銀が目標とする「持続的・安定的な2%」を大きく超えています。通常であれば、経済の過熱や行き過ぎたインフレを抑えるために「利上げ」という金融引き締め策が選択肢となります。
しかし、現在の日本経済は、賃金上昇を伴わない「悪いインフレ」の側面が強いのが特徴です。この状況で利上げに踏み切れば、企業の借入金利が上昇し、設備投資を冷え込ませる恐れがあります。また、住宅ローン金利の上昇などを通じて、景気全体を悪化させるリスクもはらんでいます。
日銀としては、賃金の上昇を伴った形での2%物価目標の達成を確実に見通せるまで、大規模な金融緩和を維持したいというのが本音でしょう。しかし、物価上昇が続けば国民の不満は高まり、利上げへの圧力も強まります。賃金と物価のバランスを見ながら、どのタイミングで政策を修正するのか。その判断は極めて困難なものとなっています。
今後の展望と生活者への影響

私たちの生活はこれからどうなるのでしょうか。希望の光と、警戒すべきリスクの両方を見据えておくことが大切です。
賃金上昇が追いつく可能性とリスク要因
今後の焦点は、名目賃金の上昇ペースが物価上昇率を上回れるかという一点に尽きます。明るい兆しとしては、深刻な人手不足を背景に、企業が人材確保のために賃上げを継続せざるを得ない状況があります。2025年の春闘(春季労使交渉)でも高い賃上げ率が実現すれば、実質賃金がプラスに転じる可能性は十分にあります。企業の価格転嫁が進み、収益力が改善されれば、その果実が従業員に分配される好循環も期待されます。
しかし、リスク要因も少なくありません。最大の懸念は、海外経済の動向です。アメリカや中国など主要な貿易相手国の景気が後退すれば、日本の輸出企業は打撃を受け、賃上げの原資が失われます。また、地政学的なリスクの高まりによるさらなるエネルギー価格の高騰や、投機的な動きによる急激な円安の再燃なども、物価を押し上げ、実質賃金を圧迫する要因となり得ます。
家計防衛策・個人が取れる対策(節約・副収入・投資)
こうした先行き不透明な時代において、私たちはただ待っているだけでなく、自ら行動を起こす必要があります。個人ができる家計防衛策は、大きく分けて3つあります。
一つ目は「支出の最適化」です。まずは通信費や保険料といった固定費を見直しましょう。また、日々の買い物ではキャッシュレス決済のポイント還元を活用するなど、賢く節約することが求められます。
二つ目は「収入源の多様化」です。現在の勤務先での昇給だけに頼るのではなく、自身のスキルを磨いてより待遇の良い企業へ転職を目指したり、空いた時間で副業を始めたりすることも有効な選択肢です。
三つ目は「インフレに負けない資産形成」、つまり「投資」です。インフレは現金の価値を目減りさせますが、株式や投資信託、不動産といった資産は、インフレに応じて価値が上昇する傾向があります。NISA(少額投資非課税制度)などを活用し、リスクを分散しながら長期的な視点で資産を育てていくことが、将来の購買力を守る上で極めて重要になります。
まとめ|実質賃金低下とどう向き合うか

政策動向を注視しつつ、個人レベルでの備えも必要
2025年6月の「実質賃金1.3%減」というデータは、多くの日本人にとって、給料が上がっても生活が楽にならないという厳しい現実を数字で示したものです。この問題の根源には、賃金の伸びを上回るペースで進む物価上昇という構造的な課題があります。
政府の最低賃金引き上げや、日本銀行の金融政策は、私たちの生活に大きな影響を与えます。これらの動向をニュースなどで正しく理解し、社会全体がどのような方向に向かっているのかを把握しておくことは非常に重要です。
しかし、外部環境の変化を待つだけでは、大切な自分の資産や生活を守ることはできません。この機会に自らの家計を見直し、収入を増やす努力をし、インフレに負けない資産形成を始める。そうした一人ひとりの前向きなアクションこそが、この不透明な時代を乗り切り、将来の安心を手に入れるための最も確実な方法と言えるでしょう。経済の大きな流れを理解しつつ、地に足の着いた備えを進めていきましょう。