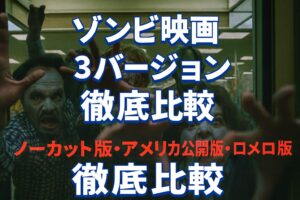1978年、ジョージ・A・ロメロ監督が世に放った一作の映画が、世界を震撼させ、そして「恐怖」の定義を永遠に書き換えました。その名は『Dawn of the Dead』(邦題:ゾンビ)。
公開から半世紀近くが経過した今なお、本作は「史上最高のゾンビ映画」として絶対的な地位に君臨しています。現代の『ウォーキング・デッド』も、『ラスト・オブ・アス』も、あるいは『バイオハザード』でさえも、その源流を辿ればすべてこの作品に行き着きます。いわば、現代ポップカルチャーにおける「ゾンビ」という概念のすべてが、ここから始まったと言っても過言ではありません。
しかし、なぜこれほどまでに本作は特別なのでしょうか? 単に「怖いから」ではありません。そこには、1970年代のアメリカが抱えていた社会の病理、資本主義への痛烈な皮肉、極限状態における人間の尊厳と狂気が、エンターテインメントの皮を被って緻密に描かれていたからです。
本記事では、この不朽の名作がいかにして生まれ、何を伝え、そして映画史にどのような爪痕を残したのか。撮影現場の過酷な裏話、マニアックな登場ゾンビの解説、そして日本独自の「ゾンビ文化」まで、そのすべてを余すところなく徹底解説します。
第1章:1978年という時代――「不安」が生んだ傑作
この映画を深く解読するためには、まず1970年代後半という時代の空気を吸い込む必要があります。本作は、あの時代の「申し子」だからです。
1. 「強いアメリカ」の崩壊と虚無
1968年の前作『Night of the Living Dead』が、公民権運動やベトナム戦争の「最中」の生々しい恐怖を描いたとすれば、10年後の本作『Dawn of the Dead』が描いたのは、祭りの後の「虚無感」でした。
70年代後半のアメリカは、ベトナム戦争の敗北による精神的後遺症、ウォーターゲート事件による政治不信、そしてオイルショックによるインフレと経済停滞の真っただ中にありました。かつての「正義の国アメリカ」の像は崩れ去り、人々は漠然とした不安と相互不信の中に生きていました。 冒頭のWGONテレビ局の混乱したスタジオ描写は、まさに当時のアメリカ社会の縮図です。「情報は錯綜し、誰も責任を取らず、システムが機能不全に陥っている」。ロメロは、ゾンビというフィクションを通して、当時の観客が肌で感じていた「社会が内側から腐っていく感覚」を映像化したのです。
2. 消費社会という名の麻薬
不安な現実から目を背けるように、人々が救いを求めたのが「消費」です。郊外には巨大なショッピングモールが次々と建設され、人々は物を買い、食べ、所有することで心の隙間を埋めようとしました。
「買い物さえしていれば幸せ」という思考停止の状態。 本作で描かれるゾンビたちは、まさにこの「消費者の成れの果て」として描かれています。彼らがなぜモールに集まるのか? 作中のピーターのセリフがすべてを語っています。
「生前の記憶だよ。ここが重要な場所だったと覚えているのさ」
エスカレーターを徘徊し、ショーウィンドウを虚ろに見つめるゾンビの姿は、スクリーンを見つめる観客自身の鏡像でもあったのです。
第2章:舞台装置としての「モンローヴィル・モール」
本作を唯一無二の存在にしている最大の功績は、ペンシルベニア州に実在した巨大商業施設「モンローヴィル・モール」をロケ地に選んだことです。
1. 深夜23時から朝までの「地獄の撮影」
低予算映画であったため、営業中のモールを閉鎖することは不可能でした。そのため、撮影はモールの営業が終了した夜の23時から、翌朝の開店準備が始まる午前7時までの間に行われました。 スタッフとキャストは、連日昼夜逆転の生活を強いられました。10月、11月の撮影時期、モール内の暖房は夜間停止されます。極寒の中、クリスマスの装飾が残る煌びやかなモールで、夜な夜なゾンビメイクを施したエキストラたちが徘徊する。 朝6時になると「通常の」買い物客のための音楽が流れ始め、スタッフは大急ぎで血糊を洗い流し、バリケードを撤去しなければなりませんでした。この過酷なルーチンが、映画全体に漂う「夢うつつのような浮遊感」と、出演者たちのリアルな疲労感を生み出しました。
2. 「ムザック」が奏でる狂気
映画の中で印象的に使われるのが、モール内に流れる軽快なBGM(ムザック)です。 特に有名なのが「The Gonk」と呼ばれるエンディング曲。ポルカ調のどこかおどけたメロディです。内臓が飛び出し、肉が食いちぎられる凄惨な地獄絵図のバックで、ひたすらに陽気で安っぽい館内放送の音楽が流れ続ける。 この「グロテスク」と「ポップ」の強烈なコントラストこそが、ロメロ演出の真骨頂です。人類の悲劇すらも、BGM付きのショーとして消費されていくような、乾いた絶望感がそこにはあります。
第3章:日米伊の奇跡的なコラボレーション
『Dawn of the Dead』は純粋なアメリカ映画だと思われがちですが、その成立にはイタリアの巨匠たちの力が不可欠でした。
1. ダリオ・アルジェントとの盟約
低予算ホラーの帝王ロメロとはいえ、巨大モールを貸し切り、大量の特殊メイクを施すための資金調達は困難を極めました。そこで手を差し伸べたのが、イタリアン・ホラーの巨匠ダリオ・アルジェント(『サスペリア』監督)です。 アルジェントはロメロの脚本に惚れ込み、ヨーロッパや日本など、英語圏以外での配給権と引き換えに出資を決定。さらに、脚本執筆の環境としてローマのアパートを提供しました。 ロメロのアメリカ的なドライな視点と、アルジェントのヨーロッパ的な耽美と過剰さが融合し、本作は奇跡のハイブリッド作品となったのです。
2. ゴブリン(Goblin)の衝撃
音楽を担当したのは、アルジェント作品でおなじみのプログレッシブ・ロック・バンド「ゴブリン」。 彼らが奏でるシンセサイザーのスコアは、恐怖を煽るだけでなく、どこか悲哀に満ちています。特にメインテーマの、脈打つようなベースラインと叫ぶようなシンセ音は、迫りくるゾンビの足音と、登場人物たちの心臓の鼓動を見事に表現しています。 米国公開版では、あえてゴブリンの曲を減らし、ライブラリ音源(著作権フリーのストック音楽)が多用されていますが、重要な局面で鳴り響くゴブリンの旋律こそが、本作の格調を高めている要因です。
第4章:4人の生存者たち――崩壊のプロセス
ゾンビ映画において、最も恐ろしいのはゾンビではなく「人間」である。この定説を確立したのも本作です。極限状態に置かれた4人のキャラクターは、それぞれ社会の異なる側面を象徴し、異なる末路を辿ります。
1. ピーター(ケン・フォリー):理性を保つリアリスト
SWAT隊員。身長196cmの巨漢で、戦闘能力が高く、常に冷静な判断を下すリーダー格。 当時のハリウッド映画において、黒人が最後まで生き残り、かつ実質的な主役としてリーダーシップを発揮するのは画期的なことでした。彼の存在は、崩壊した社会において「人種や階級といった既存のヒエラルキーが無意味になる」ことを象徴しています。 彼が漏らす「地獄が満員になると、死者が地上を歩きだす(When there’s no more room in hell, the dead will walk the earth)」というセリフは、映画史に残る名言です。
2. ロジャー(スコット・H・ライニガー):暴力に魅入られた男
ピーターの同僚SWAT。陽気で勇敢ですが、次第にゾンビ狩りの高揚感(ハイ)に取り憑かれていきます。 彼は「暴力への依存」を体現するキャラクターです。極限状況でのアドレナリン中毒は、彼から冷静さを奪い、「やったぞ!全部いただいた!(We whipped ‘em and we got it all!)」と叫びながら無謀な行動へ走り、結果として噛まれてしまいます。 彼が徐々に弱り、死に、そしてゾンビとして蘇るまでの過程は、本作の白眉です。ピーターにかつて約束させた「自分が戻ってきたら始末してくれ」という願い。蘇ったロジャーの虚ろな瞳と、引き金を引くピーターの涙は、ゾンビ映画史上最も悲しいシーンの一つです。
3. フラン(ゲイレン・ロス):覚醒する女性
テレビ局員。当初は守られるだけの存在でしたが、妊娠していることを明かし、さらに「コーヒーを入れる係はごめんだわ」と銃の扱いを学び始めます。 彼女の変化は、ウーマン・リブ運動を経た70年代女性の自立を反映しています。多くのホラー映画で女性が「悲鳴を上げるだけの役」だった時代に、フランはヘリの操縦を覚え、脱出の鍵を握る存在へと成長します。彼女がくわえタバコでヘリの燃料を確認するシーンの、なんと頼もしいことでしょうか。
4. スティーブ(デヴィッド・エムゲ):無力な知識人
ヘリのパイロットでフランの恋人。射撃も下手で、ゾンビへの恐怖心を最後まで拭えません。 彼は、平和な時代にはうまく立ち回れても、暴力が支配する世界では無力な「中流階級の知識人」を象徴しています。 彼の最期はあまりにも皮肉です。ゾンビ化してもなお、本能的に「隠れ家への道(エレベーターの壁)」を偽壁の上から叩き続け、結果として侵入者を招き入れてしまう。生前の「所有への執着」が、仲間を危険に晒すという残酷な展開は、ロメロの人間観察の鋭さを示しています。
第5章:トム・サヴィーニの特殊メイク革命
本作を語る上で絶対に外せないのが、特殊メイクアップ・アーティスト、トム・サヴィーニの功績です。
1. 「死の色」の発明
ベトナム戦争で従軍カメラマンとして戦場を経験したサヴィーニは、そこで目にした「本物の死体」のイメージを映画に持ち込みました。 しかし、彼が選んだのはリアル一辺倒のアプローチではありません。当時のフィルムの発色を考慮し、ゾンビの肌を「灰色(グレー)」に塗ることで、生気のない不気味さを演出しました。この「ロメロ・ゾンビ=青白い顔」というビジュアルは、後の業界標準となりました。
2. 鮮やかな「赤」の美学と「頭部破裂」
本作の血糊は、不自然なほど鮮やかな「ペンキのような赤」です。これはサヴィーニとロメロがあえて選んだスタイルで、コミックブックのようなポップさを狙ったものでした。 最も有名な特殊効果は、物語序盤のアパート突入シーンにおける「頭部破裂」でしょう。ショットガンで撃たれた強盗団の頭が吹き飛ぶこのシーンは、コンドームに血糊と食品を詰めて破裂させるという極めてアナログな手法で撮影されましたが、その衝撃度は今見ても色褪せません。
第6章:マニアック解説|ゾンビ・武器・車両
ここからは、本作を彩るディテールについて少しマニアックに掘り下げてみましょう。
1. 記憶に残る「名脇役ゾンビ」たち
本作には、単なる背景ではない、強烈な個性を持ったゾンビが登場します。
-
クリシュナ教徒ゾンビ: オレンジ色の僧衣をまとい、タンバリンを持ったままゾンビ化した元クリシュナ教団員。屋上の部屋でフランを襲うシーンはトラウマ級です。
-
看護婦ゾンビ: 白いナース服を着たゾンビ。そのビジュアルの分かりやすさから、ポスターやスチール写真で頻繁に使用されました。
-
ソフトボール選手ゾンビ: ユニフォーム姿で金属バットを持ったまま徘徊するゾンビ。「趣味を持っていた人間」も等しく死ぬという描写です。
-
マチェーテ・ゾンビ: 暴走族の襲撃時に、トム・サヴィーニ演じるブレイズに鉈(マチェーテ)を脳天に叩き込まれたゾンビ。頭に刃物が刺さったまま倒れ込む描写は、特殊メイクの真骨頂です。
2. 登場する武器と車両
サバイバル映画としての魅力を高めているのが、実在する銃器や車両のリアルな描写です。
-
サベージ M99: ピーターたちが武器屋から調達するレバーアクション・ライフル。スコープ付きで、ゾンビの頭部を正確に狙撃するシーンで多用されました。
-
M16A1: SWAT隊員が使用するアサルトライフル。冒頭の市街戦や、終盤の暴走族との銃撃戦で火を吹きます。
-
フォルクスワーゲン・シロッコ: モール内で展示されていた新車。ピーターたちがモール内を移動するために乗り回します。屋内の狭い通路を車が走るという非日常感が、この映画の「遊び心」を象徴しています。
第7章:暴走族の襲来とカメオ出演
物語のクライマックス、モールの平和を壊すのはゾンビではありません。略奪を目的とした「暴走族」の集団です。
1. 暴走族とパイ投げ論争
この展開には、公開当時から賛否両論がありました。特に批判されたのは、暴走族がゾンビにパイを投げつけたり、炭酸水をかけたりするスラップスティック(ドタバタ喜劇)な描写です。「恐怖感が削がれる」という声が多く上がりました。 しかし、これこそがロメロの狙いでした。彼らにとってゾンビは「恐怖の対象」ではなく「おもちゃ」でしかないのです。ナメてかかった人間が痛い目を見るというカタルシス。そして、「人間こそが最も恐ろしい怪物であり、かつ最も愚かである」というテーマは、この暴走族シークエンスによって完成します。
2. 豪華すぎるカメオ出演
暴走族のリーダー「ブレイズ」を演じているのは、特殊メイク担当のトム・サヴィーニ本人です。彼はスタントマンとしても活躍し、トラックから転落する危険なシーンなどを自ら演じています。 また、冒頭のテレビ局のシーンで、混乱する現場のディレクター役としてジョージ・A・ロメロ監督自身が出演しています(ヒゲの男性)。さらに、当時のロメロの妻クリスティン・フォレストも出演しており、まさにロメロ・ファミリー総出で作られた映画なのです。
第8章:幻のエンディングと「3つのバージョン」
『Dawn of the Dead』には、制作の経緯から大きく分けて3つのバージョンが存在し、それぞれ受ける印象が全く異なります。
1. バージョン地獄:どれを観るべきか?
-
米国劇場公開版(127分): ロメロが最終決定権を行使したバージョン。ドラマ、アクション、音楽(ライブラリ音源多め)のバランスが取れており、コメディリリーフも含んだ「映画としての完成度」が最も高いとされる版です。
-
ダリオ・アルジェント監修版(119分): ヨーロッパや日本(『ゾンビ』)で公開されたバージョン。会話シーンを大幅にカットし、ゴブリンの音楽を全編に敷き詰めた、テンポの速いアクション・ホラー仕様。恐怖度はこれが一番高いと言われます。
-
ディレクターズ・カット版(139分): カンヌ映画祭でお披露目された最長版。説明的な描写が多く、より人間ドラマに焦点が当てられています。音楽の使用箇所が少なく、ドライな印象を与えます。
2. 幻の「自殺エンディング」
実は、脚本段階でのエンディングは現在と全く異なる、救いのないものでした。 当初の予定では、ピーターは自分に向けて発砲し自殺。フランは回転するヘリのローターに首を突っ込んで自殺。無人のヘリのプロペラ音だけが響き渡って終わる……という絶望的なラストが用意されていました。 しかし撮影中、ロメロは「彼らは苦難を乗り越えたのだから、生き残るべきだ」と考えを変えます。結果、ピーターは土壇場で生きることを選び、フランと共にヘリで飛び立つ現在のエンディングに変更されました。 この変更が、本作を単なる鬱映画から「人間賛歌」へと昇華させたのです。
第9章:日本における『ゾンビ』旋風
最後に、日本における本作の受容について触れておきましょう。
1. 1979年の衝撃と「惑星」の嘘
日本では1979年に『ゾンビ』というシンプルなタイトルで公開されました。 当時の配給会社は、大ヒットした『サスペリア』にあやかり、「サスペリアPART2」ならぬ、ダリオ・アルジェント関連作としての宣伝を展開しました。 有名なのが、冒頭に追加された「惑星から怪光線が降り注ぎ、死者が蘇った」という旨のナレーションと字幕です。これは日本版独自の設定であり、本来の映画には一切出てきません。しかし、このSFチックなハッタリがかえって子供たちの想像力を刺激し、大ヒットに繋がりました。
2. テレビ放送版と声優の功績
日本での人気を決定づけたのは、テレビ放送(ゴールデン洋画劇場など)でした。 特に、内海賢二氏が声を当てたロジャーの演技は伝説的です。陽気なSWAT隊員が徐々に狂気に蝕まれ、断末魔の叫びを上げるまでの演技は、オリジナル以上に鬼気迫るものがありました。日本における『ゾンビ』文化は、こうした素晴らしい吹き替え版によって醸成された側面も大きいのです。
最終章:『Dawn of the Dead』が遺したもの
ロメロ版『Dawn of the Dead』は、映画のルールを根本から変えました。
それまでの怪奇映画における怪物は、吸血鬼や狼男といった「特別な存在」でした。しかしロメロは、怪物を「量産される大衆」として描きました。 隣人が怪物になり、その怪物もまた簡単に破壊される。そのドライで即物的な死生観は、現代のゲーム(『デッドライジング』など)や映画(『ショーン・オブ・ザ・デッド』『28日後…』など)に直結しています。
現代へのメッセージ
公開から半世紀近くが経ち、インターネットやスマートフォンの普及によって、私たちの消費社会は形を変えました。しかし、「情報や物に依存し、思考停止に陥る」という人間の本質は変わっていません。
モールを徘徊するゾンビの姿は、ブラックフライデーに群がる人々や、スマホの画面を見つめながら街を歩く現代人の姿と重なって見えないでしょうか?
ジョージ・A・ロメロは、ゾンビ映画というフィルターを通して、私たち人間に問いかけ続けています。 「君たちは生きているか? それとも、ただ動いているだけか?」
『Dawn of the Dead』。 それは、終わりのない悪夢であると同時に、人間理性の最後の砦を描いた、永遠の黙示録なのです。
※記事内のデータについて: 制作費は約50万〜150万ドル(諸説あり)、世界興行収入は5,500万ドル以上と推定されています。出演キャストやスタッフの情報は、公式クレジットおよび映画史の記録に基づいています。